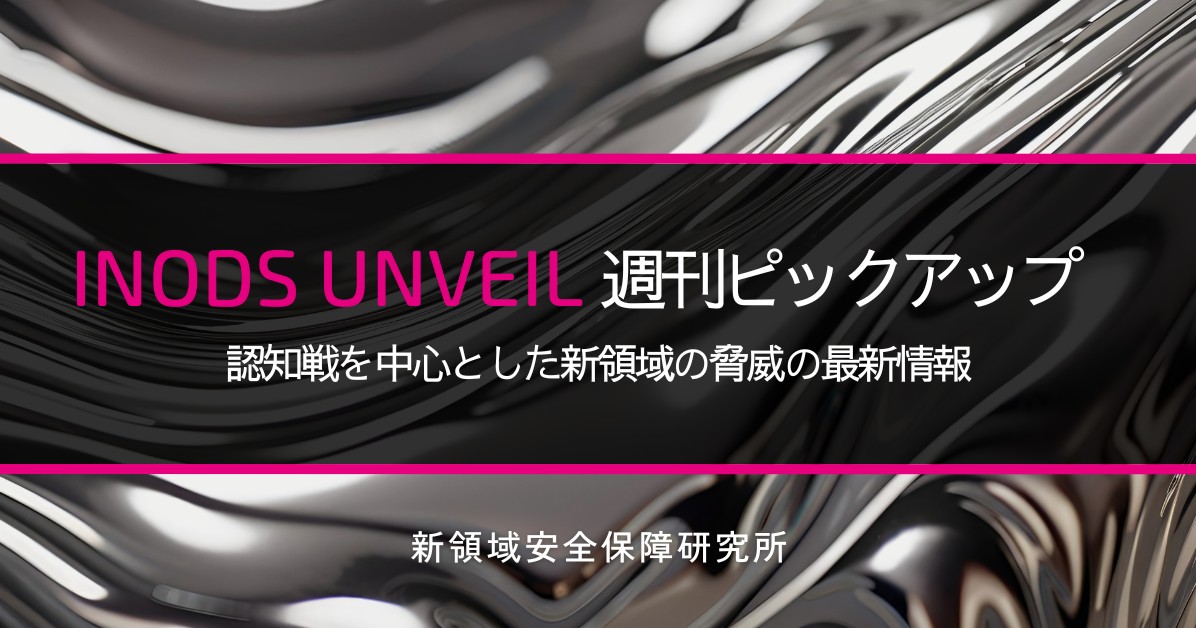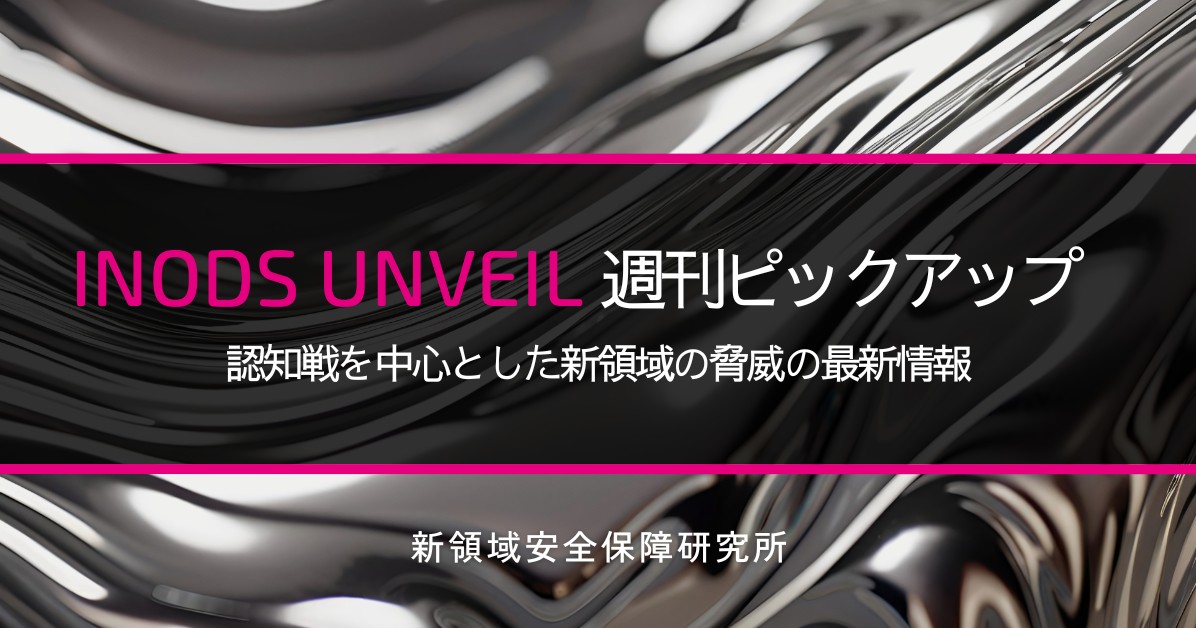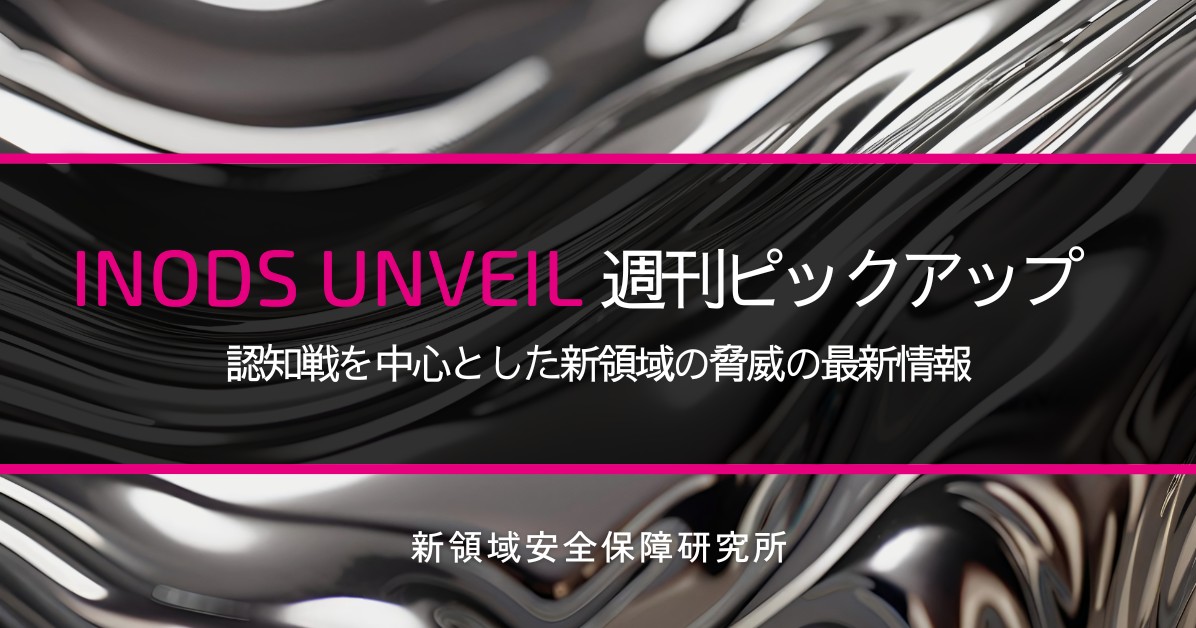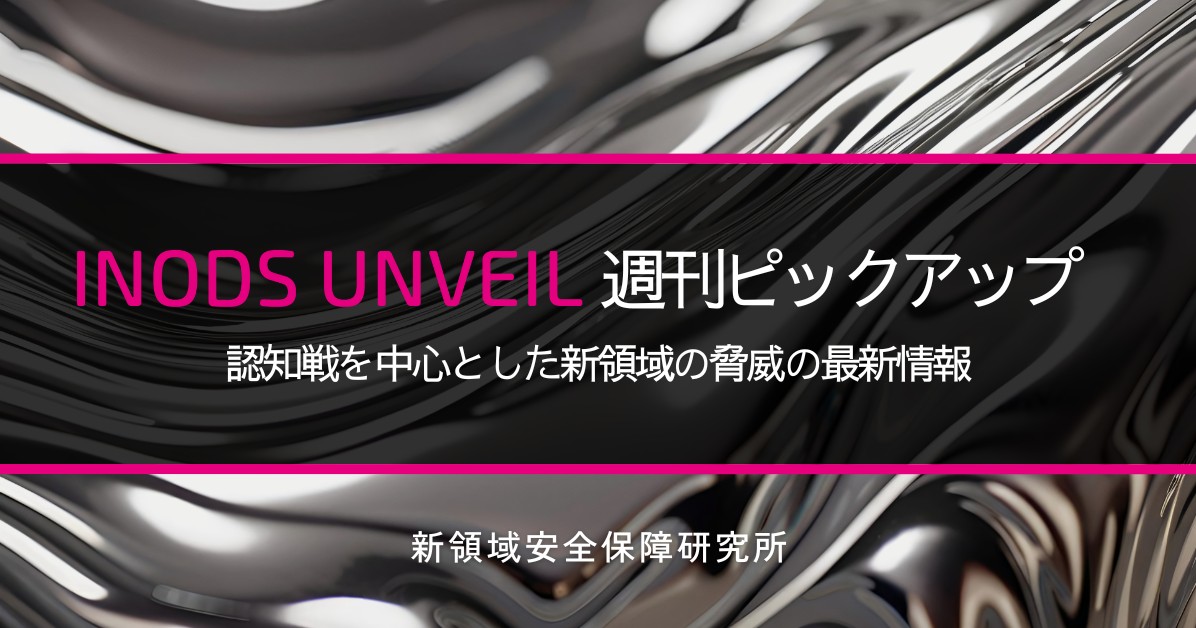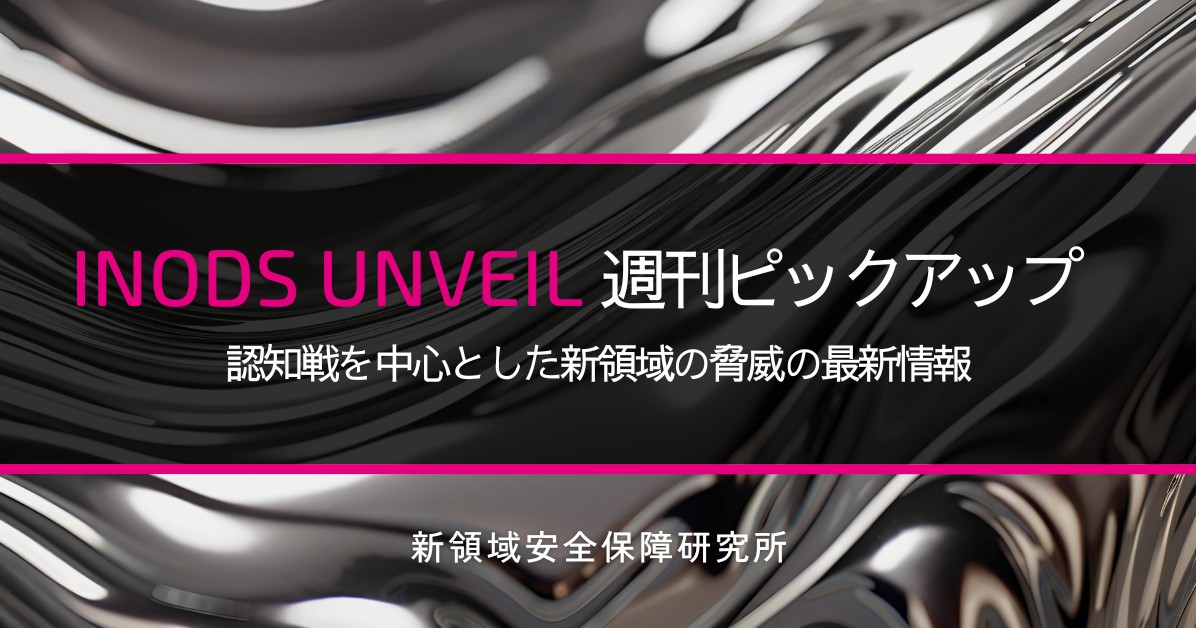【レポート】SNSでの影響工作と株価変動の関係 〜ハッシュタグとボットの影響〜 1/2
はじめに
近年、ソーシャルメディアの急速な普及に伴い、SNS上での情報拡散が社会や経済に与える影響が一層注目されるようになっている。特に、X(旧Twitter)などのプラットフォームでは、特定企業に関する話題や炎上が瞬時に拡散し、それが企業の意思決定や株価に直接的な影響を与える可能性がある。
本研究では、X上で発生した特定の8企業に関連する話題や炎上現象と、それに伴う株価変動との関係性を調査した。具体的には、各話題や炎上に関する投稿を対象に、ハッシュタグの総数や種類、ボットアカウントの割合、投稿数を詳細に算出・分析した。
その結果、ハッシュタグとボットを活用した意図的かつ協調的な情報拡散の試みが確認された。これらの組織的な活動は、企業の評判に留まらず、企業の行動や株価に対しても重大な影響を与えている可能性が示唆されている。本論文では、このようなSNS上の影響工作の実態と、それが企業の株価や戦略に及ぼす影響について分析する。
本研究では、Xを主要な調査対象としたが、実際には他のSNSやオフラインの活動と組み合わされている可能性も否定できない。しかし、株価への影響工作が行われる際、日本国内で普及率の高いXを除いて活動が展開される可能性は低く、Xを分析することが株価干渉の有無を確認する上で有効であると考えられる。
1. 調査方法
本研究では、X(旧Twitter)上で特定の企業に対する炎上や関連キーワードに関する投稿を収集・分析し、影響工作の実態とそれが企業の株価に与える影響を調査した。以下に具体的な手法を示す。
データ収集
調査対象の企業に関連する炎上や話題のキーワードを選定した。これらのキーワードには、企業名、製品名、関連するハッシュタグ、否定的な用語(例:「不買運動」「炎上」)などが含まれている。これらのキーワードを基に、特定期間内の関連する投稿を収集した。収集期間は炎上が発生した前後とし、時系列的な変化を捉えることを目的とした。
データ前処理
収集した投稿データから以下の情報を抽出・整理した。
-
投稿日次:時系列分析のため。
-
本文テキスト:内容分析およびキーワード出現頻度の算出のため。
-
ハッシュタグ:協調的な情報拡散の分析のため。
-
リツイート数・いいね数:投稿の拡散度合いを評価するため。
独自技術によるボットアカウントの識別
影響工作にボットアカウントが利用されている可能性を調査するため、本研究では独自に開発したボット判定技術を用いて、各アカウントがボットであるかを識別した。
データ分析
分析は以下の手順で行なった。
-
ハッシュタグ分析:頻出するハッシュタグを特定し、協調的に使用されているかを調査した。
-
時系列分析:投稿数や特定キーワードの出現頻度を時間軸に沿ってプロットし、炎上の発生タイミングと拡散パターンを明らかにした。
-
ボット影響度の評価:独自技術で判定したボットアカウントからの投稿数や、その拡散度合いを算出し、全体に占める割合や影響力を評価した。
-
株価データとの比較:同期間の企業の株価データを収集し、SNS上の活動指標と株価変動との相関関係を分析した。
目視による確認
定量的な分析結果に加えて、実際の投稿内容を目視で確認した。これにより、数値では捉えきれない以下の点を検証した。
-
投稿内容の確認:今回は、ざっと確認する程度で内容についての精査はしない。
-
影響工作の手法:今回は、ハッシュタグの種類などを確認。
コラム:国内でも観測されるようになったSNS・メディアを使った会社乗っ取り工作
SNSやメディアを利用した情報操作は、もはや国際的な政治や外交に限られた現象ではなく、国内の上場企業に対する攻撃手段としても利用されるようになってきている。特に近年、偽情報や誤情報を駆使し、企業の株価や評判を意図的に操作する影響工作がSNSでも観測されるようになってきている。仕掛ける側は巧みにSNSやメディアを駆使し、会社乗っ取り成功に導くケースも散見されている。
ここでは、具体事例を一つ紹介する。フジテック株式会社(以下、フジテック)の2023年に起きたケースである。フジテックは、長年にわたり先進技術を取り入れ、業界内で高い評価を受けていた。アジア圏にもビジネス展開し、収益性も安定しており、内部留保も豊富に確保していた。そして、経営は創業家が長年にわたり取り仕切っていた、典型的なファミリー企業であった。
しかし、突如として創業家の経営方針に批判的な株主グループ(アクティビスト)が現れ、SNS、ネットメディアや雑誌を利用して創業家に対する悪評を広め始めた。経営の不透明性や内部留保の使い道などが問題視され、これにより機関投資家たちが創業家から距離を置くようになった。
その後の株主総会では、創業家が株主グループに糾弾される場面が見られた。株主の利益を最大化すべきだという主張のもと、内部留保の問題が取り上げられ、さらには創業家に対する誹謗中傷が公然と展開されたのである。こうした緊急動議の結果、最終的に創業家は会社の経営から排除されてしまった。
このようなSNSやメディアを活用した影響工作は、表面的には「株主の利益を守る」行動のように見えるかもしれないが、実際には企業経営を不安定にし、短期的な利益追求のために組織を混乱させる危険性を孕んでいる。特に、SNSで広がる情報は一度拡散されると急速に信頼性が高まる一方で、裏付けのない誤情報や意図的な偽情報が多く含まれている場合も少なくない。
このような情報戦さながらの状況は、単なる企業経営の問題ではなく、国全体の経済基盤に悪影響を及ぼしかねない。企業や経営者は、SNSやメディア上での情報操作に対して敏感になり、これらの攻撃に対する対策を講じる必要がある。今後、こうした会社乗っ取りが増加することが予想される中、適切な防衛策を講じることは、企業の存続と市場の健全性を守るために不可欠である。
2. データセット
本研究では、以下の企業に関連する炎上や「不買運動」を含む話題の投稿を収集した。
-
サントリーホールディングス株式会社(以降は「サントリー」)
サントリーの社長の発言が世間で話題となり、消費者の批判を招いた。この発言をきっかけに、不買運動が発生した。 -
株式会社 明治(以降は「明治製菓」)
明治製菓はレプリコンワクチンの開発を進めていたが、これに対して消費者からの強い反発があり、炎上状態となった。この騒動をきっかけに不買運動が起こった。 -
日清食品株式会社(以降は「どん兵衛」)
どん兵衛がアンミカ氏を起用した広告に対して消費者から批判が集まり、結果として不買運動が広がった。 -
オイシックス・ラ・大地株式会社(以降は「オイシックス」)
オイシックスの当時の会長の発言が問題視され、消費者からの批判を招いた。不買運動がこの発言をきっかけに始まった。 -
キリンホールディングス株式会社(以降は「キリン」)
キリンが成田悠輔氏を広告に起用したことが世間の反発を招き、炎上が発生した。この広告をめぐる批判が不買運動に発展した。 -
株式会社ニトリホールディングス(以降は「ニトリ」)
ニトリが政府との賄賂疑惑を報じられ、これが消費者に問題視され、不買運動が起こることとなった。 -
小林製薬株式会社(以降は「小林製薬」)
小林製薬の製品による健康被害が報告され、消費者はこれを受けて同社製品を避けるようになり、不買運動が拡大した。 -
株式会社ドトールコーヒー(以降は「ドトール」)
ドトールの新たに起用された役員が批判の対象となり、その結果不買運動が広がった。
収集したデータセットの詳細は表1に示す。複数のキーワードのうち、いずれか1つでも該当する投稿を収集した場合、それらのキーワードは「or」を用いて記載した。
なお、今後データセットを表記する際には、簡略化のために表1に示された最初のキーワードのみを使用した。また、各データセットの概要については表2に示す。